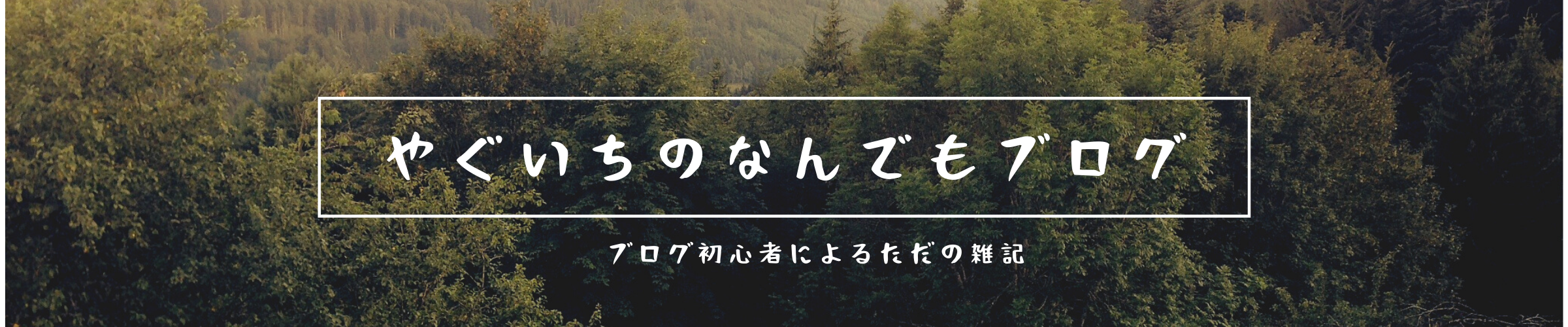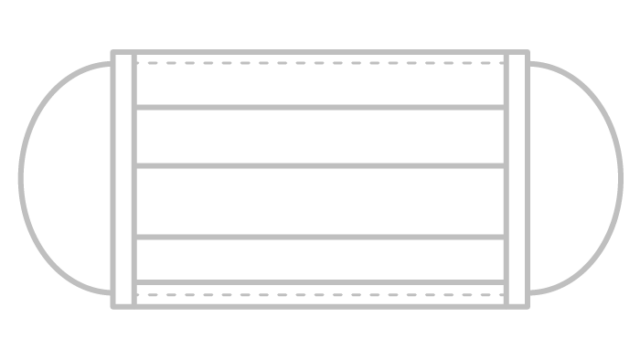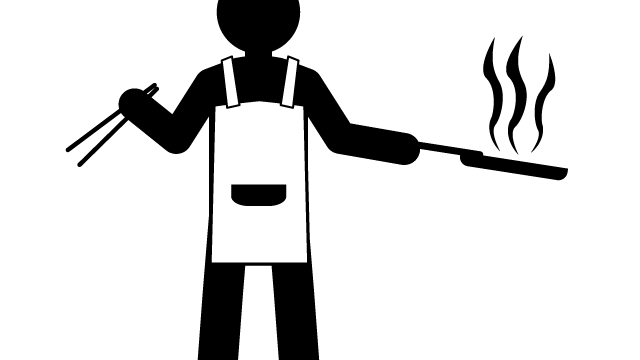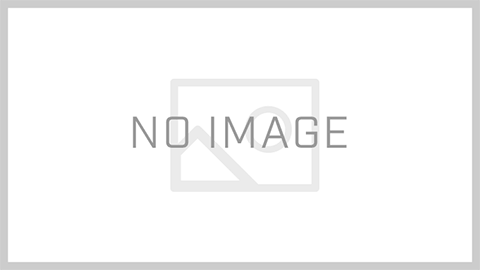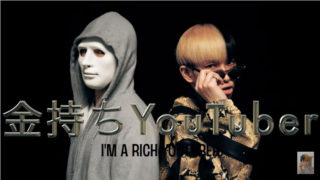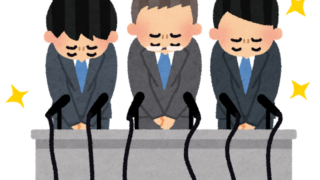どうも やぐいちです!
先日、娘の誕生日のお祝いでケーキを食べました!
ちょっと前まで赤ちゃんだった気がするのに、もう6歳。
子供の成長は早いです!
というより、大人の1年があっという間なのかもしれませんね・・・
そんな子供にとっては嬉しい誕生日ですが、みなさんケーキは食べます?
【ケーキに年の数だけロウソクを立ててハッピーバースデーソングを歌う。】
当たり前の日常ですが、日本ではいつから当たり前になったのでしょう?
というのも、いちおう神道や仏教の風習が根付いている日本国なので、昔からあった日常では無いのは何となく予想がつきますよね?
(いちおう、と付けるのは日本人の大多数は無宗教だからです。神道、仏教の風習が根付いてるとはいえ、信者では無い方が大多数です。)
誕生日には誕生日ケーキを食べる。
別に珍しいことではありませんし、普通のことですが、
日本で浸透していったのはいつからなのか?ちょっと気になったので調べてみたいと思います。
誕生日ケーキの発祥はギリシャから?
誕生日ケーキの発祥はギリシャであるという説があります。
古代ギリシャでは月の女神アルテミスを祝うために丸いケーキを焼き、ロウソクを立て、祈りました。その際にロウソクから立ち昇る煙が天上の神に願いを届ける、とされていたそうです。

発祥はドイツから?
個人の誕生日をケーキで祝うようになったのがいつからなのかは諸説あるようです。
その中のひとつとしてドイツ発祥の説を紹介します。
15世紀のドイツではキンダーフェストと呼ばれる子供の誕生会が行われていました。
当時の人は悪霊は子供の誕生日に襲ってくると考えていました。
悪霊から守るために、誕生日ケーキにロウソクを灯し、一日中神に祈りを捧げたそうです。
無事に一日が終わると、夕食後にみんなでケーキを切り分けて食べました。
その後、誕生日にケーキを食べる習慣は19世紀になってからアメリカに伝わっていきます。
お菓子メーカーの宣伝効果もあり、アメリカで今のようにカラフルなケーキや年の数のロウソクを立てて祝う、という風習が広がっていったようです。
日本ではいつから?
では日本ではいつから習慣化されていったのでしょう?
以外に新しく、第二次世界大戦の後に日本に文化としてやってきます。
GHQの施策として流入したということです。
ただ、日本では数え年で年齢を数えることが大衆に浸透しており、なかなか普及しませんでした。
昭和25年1月1日に年齢のとなえ方に関する法律が施行され、誕生日をもって年齢が増えていくことが一般化され、誕生日を祝うようになり、すこしづつ現在のかたちになっていったそうです。
日本独自の誕生日のお祝い事は?
誕生日のお祝い事が海外からの流入だけですと、なんだか寂しくなってしましますが、ちゃんと日本にも誕生日のお祝い事はあります。
それが七五三になります。
室町時代からはじまり、現代も続く風習です。
今のように医療の発達してない昔は供が産まれてすぐ亡くなることが多く、生後3年ほど経ってから戸籍に登録することが一般的でした。
そして無事に3歳、5歳、7歳と成長してくれた際に神社や寺に行き、無事に成長したことの感謝とこれからの健やかな成長を神様に願う、これが七五三の由来になります。
産まれてきた赤ちゃんが元気の育つのは、ある意味当たり前の現代日本ですが、乳児死亡率が高い国はいまだに存在します。
調べてみてビックリしたのですが、日本でも以前は乳児死亡率はすごく高かったのです。
日本では1989年から統計を取っているのですが、1989年(明治32年)のデータによると、乳児死亡率は
153.8人/1000人 ということでした。
10人に1.5人が生後1年未満で亡くなっていたそうです。
ですから、明治以前はもっと死亡率が高かったのかもしれません。
七五三を迎えられるということは、ある意味奇跡でもあり、大変喜ばしいことだったんですね。

まとめ
誕生日祝い、調べてみるとふかーい歴史がありました。
祝うことも、ケーキを食べることも、実は最近からの風習なんですね。
現代人は色んなスタイルがあるからみんな統一ではないかもしれませんが、
こういった誕生日を祝う風習は残しつつ、日本独自の文化も廃れないようにしていきたいですね!
子供の成長は喜ばしいことです。年々できる事が増えて大きくなっていく姿を見ていくのは何よりの楽しみでもあります。
ただ、誕生日にハロウィンにクリスマス、そしてお正月・・・
毎年やってくるケーキやプレゼントやお菓子の準備、お年玉と・・・親は大変です・・・
まあ、子供たちが喜んでるからいいんですけどね!www
特に男親は娘に甘くなってしまうので奥さんに叱られますwww
ではまたっ
終わり!!!